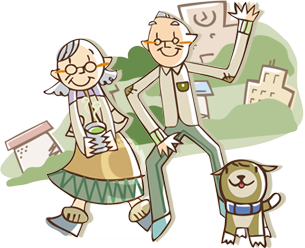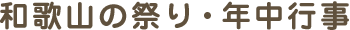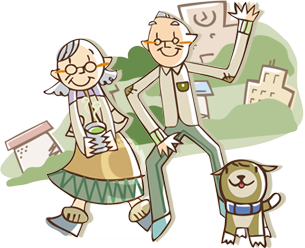由良町(衣奈)
地元で「衣奈祭」と呼ばれる
大漁・豊穣祈願の祭り。
衣奈八幡神社、浜の宮(お旅所)において、
10月14・15日に行われていたが、最近は10月の第2土・日曜日に行われる。
14日の内祭りは笠揃いといわれて、各地区で行われる。 15日の本祭は、午前8時、三尾川の鰐鼻(和仁・王仁)が到着、9時から総代、区長、招待者の神殿式が行われる。その後24人の御座衆は、出立の儀式を行う。 御座衆は黒装束と呼ばれて家紋を染め抜いた黒の素襖を着て侍烏帽子姿で、酒の肴は冬瓜膾(かもうりなます)を左手の甲へ乗せて食べる儀式を受け継いでいる。 10時から社務所の前庭で四明、白装束、お弓のお祓いがあり、続いて御輿舁や青年会役員のお祓いが行われ、神殿に場所を移して御輿に御霊移しが行われ、お旅所へ御渡りが行われる。
御渡りの順は、鰐鼻(2人)、獅子頭(2人)、四明(白装束で大榊や幣を持つ4人)、白装束(矛を持つ5人)、神饌・唐櫃、御座衆(太刀・金幣・弓、矢などを持つ24人)、みこし太鼓(2人)、前の綱、御輿、後の綱、お弓(青い着物に白の羽織・袴13人)、神主、供、総代、区長と続く。
お旅所に到着すると、黒装束と白装束は両側に分かれた桟敷に座り、御輿が安置され片側に白と紺の幕をした後、三尾川の鰐鼻やお弓が警護の役割をし神主、獅子頭、白装束が並んで、神主が神饌を供える。 神主以外は檜葉を口にくわえて物を言わずに取り次ぐ。神主の祝詞奏上の後、巫女の舞が奉納される。
正午近くから各地区の余興が奉納される。 行事は年によって違い、早朝の練り上がり、次いでお旅所の入口まで警固(あいさつ)と打ちはやしなどをして県道を下がって行く練り下がり、次いで下から来る本番を練り込みという。
<奉納行事>
衣奈(東);打ち囃し(片面打ち=一人打ち)、稚子踊り
衣奈(西);打ち囃し(両面打ち=二人打ち)、獅子舞
小引(小引・戸津井);打ち囃し、童子相撲
三尾川;打ち囃し、餅搗き踊り
大引;打ち囃し
神谷;打ち囃し、稚子踊り、獅子舞
吹井(ふけ);唐船
奉納行事が終わると、おもどり(還御) が行われる。 神殿から御霊移しが行われ、御輿が宮へ戻るが前後の綱は引っ張らないで清々と担がれて行く。 打ち囃し等の行列も途中で解散する。
社務所で納めの式に参加するのは、御座衆、四明、白装束、総代、区長などで尚武の盃を執り行う。また、衣奈の打ち囃しのみ宮で奉納して儀式が終了する。
祭礼の歴史は古く、寛文4年(1664年)の衣奈八幡神社の祭礼次第によると八月十四日、十五日に行われたと記されている。
以前は神事に神の相撲が奉納されたが今は無くなった。 子供の数が激変し、以前はくじ引きをして参加者を決めていたが、今は役員が頼みに行ったり、女子の参加も増えてきている。 各地区間の相互援助も検討されている。 |