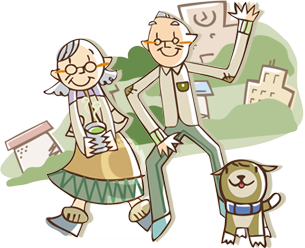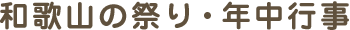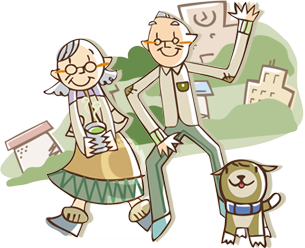和歌山市(伊太祁曽)
卯杖祭(うづえまつり)と呼ばれている。
伊太祁曽神社拝殿で
1月14~15日に行われる厄除けと農作物の豊凶占い神事
3つの要素が複合された神事
年が明けた最初の兎の日にお供えする杖、卯杖で邪気を祓う神事(卯杖は、梅の若枝を束ねてつくる)。
小正月に小豆粥を食べる習慣。
粥占い神事;竹筒を沈めて中に入った粥の量で占う神事。竹筒17本でお米の品種17種で占っていたので、今も17品種にしている。JAの方にこのあたりでよく作られている品種17種を選んでいる。14日の夜に占いをして15日の早朝に割って中を見て結果が出る。そのグラフを作って配り、その結果を見て、植木市でその苗を買って帰り、田植えをした、とされる。田んぼも減ってきてるので、5年くらい前から、果物等も15品種くらい占っている。
①修祓 ②本殿報告 ③鼎前祈願 ④鼎火入れ ⑤管入れ ⑥管出し ⑦本殿奉奠 ⑧翌暁の管割り ⑨拝殿への展示。
14日20時から卯杖、米、小豆、清酒等供えられた前で、本殿脇の神事の場で、鼎の中で小豆が煮立ち、粥占い神事が始まる。3本足の鼎も天保6年に寄進された130年余の歳月が経過したもので、「吉兆、豊年万作、豊年万作」と唱え言が響き渡る。本殿前で、宮司が粥占い神事の開始を五十猛命の御魂に報告する。
長さ一尺ほどに切った清浄な竹の筒17本を用意し、鼎で小豆を煮立て、洗い米やモチを入れて煮あげる。その中に竹筒を沈める。その竹には十数種の米の品種が書き込まれていて、どの筒に最も多くの小豆粥が入ったかによって神意を伺い、今年の豊作が約束された品種とする。
約30cmの長さの17本の竹筒が煮えたぎる鼎の中に沈められる。さらに小豆粥をどの筒にも満遍なく注ぎ、ずっしりと重みを増した竹筒がそろそろと引き上げられる。
引き上げられた竹筒は、しばらく冷まされ、梅の楉で作られた卯杖、小豆粥をかけた重ね餅と共に、本殿に供えられる。翌15日の払暁に真っ二つに割られて拝殿にかかげられる。
社務所から「山東の宮おくだのうつし」と刷られた紙が集まってきた人々に配られる。
またこの頃、「山東の裸まいり」という成人儀式があり、太平洋戦争が始まるまでは、成年に達した紀ノ川筋の男性は、1月15日の夜、下帯一つでこの山東の宮に詣でることが慣例とされていた。現在、また地元のジョギングや、野球少年達で復活されつつある。
とんど焼き;火を起こして、とんど焼きを行なっている。 もともとは厄除け祈願の祭りであり、小正月に小豆粥を食べると魔除けになる信仰があり、厄除け祈願を行なっている。
日本書紀にも登場しており、もともとは朝廷儀式の一つであり、日本書紀には持統天皇三年正月初卯の日に、大学寮から卯杖を献じたとある。
|