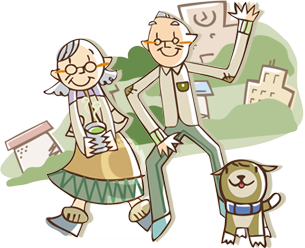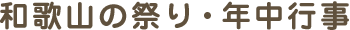和歌山市(和歌浦)
夏越の祓(なごしのはらえ)は、天神祭の本宮(7月25日)に行われる行事の1つで、「輪くぐり」とも呼ばれている。
罪や穢れを祓い清める「大祓い」の神事は年2回行われ(和歌浦天満宮では7月25日と2月3日)、そのうち、夏のものを「夏越の祓」という。
夏は食あたりや体調不良にならないように、特に気を付けなければならない時季である。夏越の祓を行い、気づかぬうちに犯してきたであろう罪や穢れを心身ともに祓い清め、無事に夏を乗りきれるようお祈りする。
【行事の順序】
修祓(お祓い)
.降神ノ儀・・・神籬(ひもろぎ)(榊を立て御幣を飾ったもの;神道では、それに神霊を招き、祭祀の対象とする)に神様をお招きする。
.献饌(けんせん)…神前にお供えをする。
.祝詞奏上
.切麻(きりぬさ)(お祓いする道具)配布…切麻とは、麻と紙(奉書紙)を小さく切ったもの。人形も一緒に半紙に包んで一般参列者に配る。
解縄(ときなわ)…神職2名で、一人は麻(縄状のもの)を解き、もう一人はあらかじめ切れ目を入れておいた羽二重の布を裂く。8回ずつ交互に行う。
自祓(じばらい)…切麻で左・右・左と自分自身を右手でお祓いする。自祓の後、切麻を唐櫃に入れる。
撤饌(てっせん)…神前の供物を下げること。
昇神ノ儀
<祭典終了>
祭壇を撤去する。
和歌山雅楽会の楽人(がくじん)が道楽(みちがく)を演奏する。笙、篳篥(ひちりき)、竜笛(りゅうてき)。楽人、巫女(切麻(きりぬさ)や人形(ひとがた)・車形代を入れた唐櫃(からびつ)を竹の担い棒にくくりつけ、2人の巫女が担う、神職、参列者が、茅ノ輪を左回り・右回り・左回りに3回くぐる。列をなすので、大きな円を描いて回る。
本殿に唐櫃をお納めする。
宮司の話(このお祭りの意味を説く)。
式が終わってから詣でる人は、個々に人形をいただき、同様に左、右、左と茅ノ輪をくぐり本殿にお詣りする。
お祓いされた人形・車形代は、境内でお焚き上げをし、その灰を海に流す。
6月30日に行う神社が多いが、和歌浦天満宮では天神祭(菅原道真の月命日・25日に催される全国の天満宮の祭)と日を合せて、7月25日に行っている。午後6時から7時過ぎまで。 天神祭は7月24日(宵宮)、25日(本宮)。
|