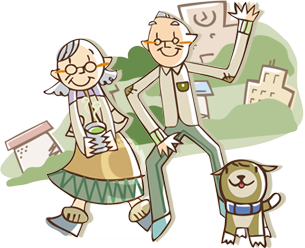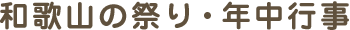橋本市(隅田町)
地元で、「管祭」と呼ばれている。
管祭とは、小豆粥占い(あずきがゆうらない)の占いの神事で、その年の稲作の豊凶を占うものであり、江戸中期から伝わる。
隅田八幡神社境内において、
1月15日(小正月)午前5時から行われる。
前日から、お米と小豆、そして神饌(酒、魚、野菜、果物など)を神前にお供えしておく。また、神事に使う小竹管(しのめくだ)3本(長さ約20㎝、直径約2.5㎝;それぞれ縦に割れている)を筏の形に組み、麻緒(麻の紐)でくくっておく。これら3本の竹の管は、「早稲(わせ)」、「中稲(なかて)」、「晩稲(おくて)」を意味し、早稲には1つ、中稲には2つ、晩稲には3つ、それぞれ穴を開けて区別している。
15日早朝、前日から絶やしていない「とんど」の火をもらい、粥を炊く薪の焚き付けにする。(藁に火を付け、持ってくる)
お供えしていたお米(一升)と小豆(5合)を大釜(5升釜)に入れ、午前5時より炊き始める。(水は神社の明(あか)井戸より汲む) 以前は、江戸中期の年号「宝暦」が刻まれた鼎(かなえ;金属製の器で、3本の足が付いている)を使っていた。粥を炊くのは隅田神社の宮司で、現宮司はもう50年位この神事を行っている。
粥が煮えたぎった頃、筏に組んだ竹筒と重しの石を小豆粥の中に入れ、数分後に引き上げて神前で竹筒を開き、その中に入った粥をそのまま拝殿に展示する。
参拝者が自身でそれぞれの筒に入った小豆粥の分量を見て、その年の稲作の品種を何にすればよいかを占う(小豆粥より引き上げられた小竹管は一月の末ごろまで展示される)。。一般に、米粒がたくさん入っているものを、その年の品種に選ぶ。また、人にもよるが、小豆が少ないのは、「になせ(出来の良くない米粒)が少ない」に通じるとも言われている。
出来上がった粥は、参拝者にふるまわれる。以前は、とんどの火をもらい受け、今年一年無事に暮らせるようにと15日の朝各家庭で小豆粥を炊いていたものだが、今はその風習もなくなりつつある。この神事は、粥を朝食に食べてもらいたいと早朝より行われるもので、午前10時くらいには大釜の粥が全てなくなる。
小豆粥を炊く時、その炊き口が南になるようにするのが習わしである。
<とんど>
1月14日、しめ縄等のお正月のお飾りやお札を神社で燃やしてもらう。この時の火をもらって管祭の小豆粥を炊く。 とんど焼きでいぶされて真黒になった橙を、家の庭に転がしておくと痛風に効くといわれ、それをもらいに来る人もいる。
|