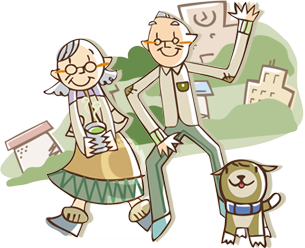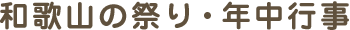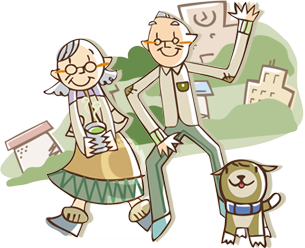印南町(印南)
地元で「
印南祭」と呼ばれる。
山口八幡神社境内、お旅所及び印南港内、各地区の地方において、
10月1日に宵宮が、10月2日に本宮が行われる。
神霊を招き山海の珍味を供え、災厄から逃れ生産を高め、悪霊を追放し平和の招来を祈願するもの。
印南祭は日高地方では御坊祭に次ぐ賑やかな祭で、旧稲原村の西山口と印南町 浜・地方・津井と旧名田村 楠井・上野・野島の七組を氏子とする。
9月28日に幟立て、10月1日の宵宮、2日の本祭の順で行われ、宵宮は印南町の4組が神社へ詣り、名田の3組は地下廻りをする。
本祭早朝、先ず野島が地元の浜へ集まって獅子舞のあと上野へ向かう。上野は野島の境まで出迎え、野島・上野が楠井へ向かうと楠井は上野の境まで出迎え、次に津井が迎える。 そして、印南の浜も加わって印南町の印定寺へ入り、屋台を預け、幟のみを持って山口八幡神社へそれぞれ宮入する。
境内では、宮起しと称して各地区の幟を立て、神輿が印南川右岸を通って浜辺へ渡御をはじめるが、この時、野島の仮家氏が 「お立ち」 と言わなければ発御出来ない習慣がある。 印定寺の手前まで来ると、各組の屋台が出迎え、また翁の面も出迎えるが、この面が出なければ行列は進めない。
お旅所では、お仮屋を設けて神輿を安置し、神事が終わると先ず地方のケンケン踊りが奉納されるが、これは、万治年中(1660年頃) はじまった雑賀踊りといわれる。
その後、奴踊・獅子舞などが奉納され、お戻りになるが、この時に屋台をぶつけ合ってはげしいせり合いがはじまる。
神事の重要な役割を担っている雑賀踊り(ケンケン踊り) については、戦国時代、和歌山市一帯を治めていた頭領 雑賀 孫一が1577年、織田信長の軍勢を追いやった祝いに3月3日、矢の宮神社で踊ったのが 「雑賀踊り」 だと言われている。その踊りが印南町の地方区が伝承していた。 後に豊臣勢に敗れ、印南に身を寄せた雑賀衆の末裔が、この 「雑賀踊り」 を伝えたとされている。
1658年、この踊りを踊れる許可を紀州藩に願い出たという古文書の記録がある。
その時から地方区では、印南祭のなかで、1番目に奉納と言う役割を、今日まで三百五十年も継承している。
行事食として、
以前は本なれ、早なれを桶に漬けたが、今はさば寿司を作る程度。
|