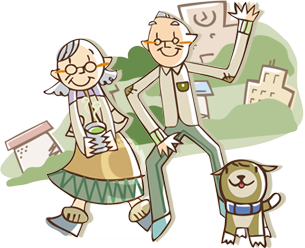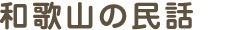国主淵(くにしぶち)の生き面
出典:貴志川町史
発行:貴志川町
昔、ある年のこと、貴志(きし)の谷一帯に、久しく雨が降らなかった。
日照(ひで)りが続いた。
諸井堰(もろいぜき)からくる用水も絶えた。まわり一里(いちり)あまり、広さ一七町といわれる平池でさえ、池底は、ひびわれ、水草は干からびていた。
それでもなお、日はカッカッと照りつけて、すみきった空には雲のかげすらなかった。
田は枯れはてた。
家々の井戸水にも、事欠くようになった。
きょうもまた、平池の堤(つつみ)へ、村人たちは、麦わらを持って集まっていった。
雨乞(あまご)いである。
高野山からタバッテきた、貧者(ひんじゃ)の一燈(いっとう)の火も着いた。甘露寺(かんろじ)の方に、西日がまったく沈んでしまうと、あたりは急に暗くなった。
闇夜の中に「パチ、パチ」と、からをはぜて鳴る、麦わらの炎だけが息づいた。
平池の堤に、人びとは、火を囲んで、般若心経(はんにゃしんぎょう)を一心に唱えた。
かんじーざいぼーさつ、
ぎょうじんはんにゃ、
はーらーみった。
じーしょうけんご
うんかいくうど・・・
いつまでも、祈りの声は続いた。
さっきまで、焼けつく太陽をうけて、あたりの草は、暗闇の中にムッと熱かった。
最後の火がどっと燃えたぎり、やがて尽きてしまうと、読経(どっきょう)の声も低くなり、またひときわ高くなって、終わったようであった。
人びとは、あぜ道をひとすじに、並んで帰った。
闇の中に赤く天をこがしているあの火は、北村の雨乞の火だ。あの火は井ノ口、西谷池あたりだろう。北のあの火は、行者山へんと知れた。
「いったい、いつになったら、降ってくれるんやろか。」
「ほんの、ひとしずくでもええ、降ってくれたら、ええんやけどなあ」
人びとは、同じ思いで歩いていった。乾ききった田の土が、暗闇に白っぽく浮かんで見える。
「ここの田ァ、民右ヱ門はんとこの田ァや」
「あそかあ、藤兵ヱはんの田ァや」
「そこァ、兵右ヱ門はんとこの田や」
「こかぁ、喜左ヱ門はんとのや」
ひとつひとつ数えながら、田の水を涸らすまいとした苦労のひとつひとつを思い出していた。もうとっくに、桶で溝っこをかすった。家の井戸、野井戸からも汲み上げて運んだ。
涸れ尽くした貴志の谷界わいで、深い水をたたえた所が、ひとつところだけあった。
それは、国主淵であった。
貴志川が、大国主の命をまつる、大国主神社の下を流れるところ。ここ、国主淵には、岸の大木が、どんよりとした、青黒い水をおおって、昼なお暗く、烏帽子(えぼし)岩、鞍懸(くらかけ)岩、天狗岩、龍宮岩のあるあたりは、最も深くて、人びとは、国主淵と呼んでいた。平池の底と通じているといわれる龍宮岩の奥深くには、大国主明神の使いである大蛇が住んで、人びとは、ここを恐れていた。
「もう、しやない。国主淵をかすらんか」
「そうや。もうあかん。こうなったら、淵の水をかすりよそらェ」
村人たちは、この国主淵の水を汲み始めた。おうこで荷ない桶をかついでは、すこしずつ運んでいった。
かつては、人びとの恐れて、近づけなかった淵の岸でさえ、しだいに、干上がって、岩のすそをあらわしていった。
その時である。
ある人は、そこに異様なものを見た。
龍宮岩の水の奥に、大木が横たわって、その様は、大蛇の姿とも見えたのだ。
「龍宮の入口ィ、おーきな木ィや、はさまって、水の湧き口、とめてるっちゅうこっちゃ」
「その木ィ、どけやなんだら、もう、水ァ、のうなってしまうど」
「だえぞ、あの木ィ、どけてくれんかなァ」
噂は、広がり、互いになげきあう声と変わった。しかし、神の怒りを恐れて、再び、国主淵へ近よろうとする者がなかった。
そのころ。
貴志の荘、小野村の郷士、橋口隼人(はしぐちはやと)の家に客人として、世話をうけていた、桜井刑部(ぎょうぶ)という武士がいた。
「日ごろは、恩義をこうむりながら、お礼をするなにものもござらぬ。ただ、拙者も武士、いささか武芸の心得もござる故、大木とやら、大蛇とやらを除いて進ぜよう。お任せ下され。」
「それは、すまんことで、ございますのし。ほやけども、わしらの恐れている大蛇のことやよってにのー。気ィつけて、いたーかひてよー。」
人びとは、桜井刑部の好意をうけて、その身を案じつつも、かすかな望みをここに託したのであった。
死をかけて、桜井刑部は、橋口家、重代の志野のなぎなたを、小脇にかかえ、烏帽子岩から、淵の水へと身をおどらせていった。
大蛇の住むという淵の水は、青くよどんではかり知れぬ深さをたたえている。
あの横たわるものは、蛇か、木か。
刑部は、水をけり、抜き手を切って、近づくと、この大なぎなたをふりかぶり、満身の力をこめて、切りつけた。
と、みるみる、動いた。
大蛇だ。
刑部が構えなおした、その時、岩の下からドッと、濁水が、ほとばしった。
らんらんと、光るまなこ。形相おそろしくいどみかかる大蛇にむかって、一撃。右に、左にかわしては、また一撃。
血潮が、目の前をおおった。
大蛇は、荒れ狂った。
吹き出す渦にもまれながら、刑部は、そこに動きまわる生き面を見た。
一つ。二つ。三つ。
大蛇と戦い、泡立つ波間を縫っては、これを掴みとり、
ひとつ。ふたつ。みっつ。
と、手にして、水面に浮かびあがった時、怪しげな風、淵の面を撫でて、空はまっ暗となった。
ポツリ、ポツリ。
大粒の雨が、水面をたたく。
ほっと、ひと息ついた時、ゴォーッと水鳴りの音がして、あっと思う一瞬、かの志津のなぎなたは、水中深く吸いこまれていった。
雷が、光った。
しのつくばかりの大雨となった。
濁水は、溢れて、川は、走った。
貴志の谷の草木は、生きかえった。
人びとも、生きかえった。
村人たちは、喜びのおもてを、雨にうたせながら、いつまでも、田の稲を見つめていた。
桜井刑部の得た面のうち、ひとつは、高野山に納めた。小野村は高野領であった。ひとつは、虎伏山竹垣城の浅野の殿さまにさし上げた。残るひとつは、橋口家の宝として伝えられることになった。
その後、貴志の谷が、ひやけ(日照り)の年、橋口家の当主、この面をかぶって、神前で能を舞えば、空かきくもって、たちどころに、雨が降ったという。
この面は橋口家当主より余の者がかぶると面の精気に当たって、病むのが常であったという。
浅野侯に献上した、翁(おきな)の面は、次の紀伊国守、徳川侯に伝わった。
やはり、生き面のこととて、これをかぶって、最後まで能を舞い終える者がなかった中に、十河(そごう)源左衛門、この面をつけて舞い終えたので、時の領主、その剛気をめでて、面を与えたという。
オイは、三月、もり物三本。
貴志の大飯(おおめし)、見にいこら。
いつのころからか、大国主神社、四月三日の祭には、大飯なる盛物を、大国主神社に、奉納するようになった。
そのひとつは、明神の使い、大蛇の住む、国主淵に供えるのを例とした。
貴志川は、きょうもかわらぬ、清らかな流れをみせている。
リンク