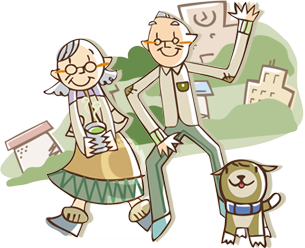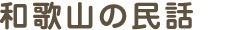次郎四郎の話
出典:金屋町誌下巻
発行:金屋町
昔、長谷川(はせがわ)に母に死に別れた哀れな兄弟がいた。兄は次郎(六つ)弟は四郎(四つ)といい、山仕事の父と三人暮しであった。毎日きまったように弁当をもって出かける父親を見送っては、二人だけの生活が始まった。「兄ちゃん寒い」との訴えをきいてはハアハアと息をかけてやさしく弟をいたわった。おひるが来れば朝の冷たい御飯を二人で分け合って食べ、食事がすむと「兄ちゃん、お母さんとこへいこう」「うん行こう」と裏山へ登って形ばかりのお墓へ草花を摘んでお供えし、「お母ちゃんはなぜ死んだの」と抱きつく兄弟であった。しかし、二人の生活ではこの時が一番楽しいときであった。陽は西に傾きかけると、次郎から「お父さんを迎えにいこう」と四郎の手をとっては山裾の一本橋にたたずんだ。そんな二人の姿には里の人々も涙を誘われた。
ある日、めっぽう寒い冬の日であったが、いつものように父親を送ってから二人はお互いの体温で暖めあいながら昼飯をとったが、四郎が「温いお茶を飲みたい」「うん、ぼくも」といったが、思い直して「お母ちゃんとこへ走っていこう、そしたらぬくもる」と次郎は弟の手をとり、駆け出した。裏山の寒さもこの二人にはきびしかった。かじかんだ手に息をかけている四郎はふと母親の乳房をまさぐる温かさを思い出した。「兄ちゃん、ここを掘ってみよう。お母ちゃんが温いよ」と呼びかけるので、次郎も母の温かさを思い出した。そして二人はそこを掘り出した。しかし、幼い二人だけでとうてい掘れるものではなかった。ひびの手からは血さえにじみ、出てくる大きな石をとりのける力はなかった。精魂(せいこん)がつき、二人は掘るのを諦め「お父ちゃんとこへいこう」といつもの一本橋を渡って山へわけてはいった。日は暮れて父親が帰ったが、二人の姿は見つからない。二人の帰って来ないことに不審をいだいて心あたりを捜してまわったがどこにも二人の姿を見つけることはできなかった。里の人にきいて見ると夕方一本橋を渡るのを見た人があったが、その後の消息を知った者は一人もいなかった。さあ大変だというので、里の人たちは手に手に松火(たいまつ)を持って山中をさがし求めた。「次郎、四郎」と呼びかけたが、山彦(やまびこ)が戻ってくるだけで空(むな)しいものであった。頂上に登って火を焚いて「次郎、四郎」と呼んだが、帰ってくるものはこだまだけで二人の行方は全く手がかりがなかった。三日、四日と火を焚き続けたが空しく、「お母さんが迎いに来たのであろう」と捜索をあきらめねばならなかった。
それから毎年七月が来ると山上で火を焚き「次郎、四郎」と呼んで二人の霊をなぐさめた。それがいつの頃からかお盆の十五夜、送り火として焚くようになり、これをやめたら悪病がはやり、作物が実らないとされ、今も続いて子供たちの手でこの行事を続けている。
リンク