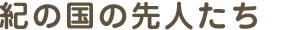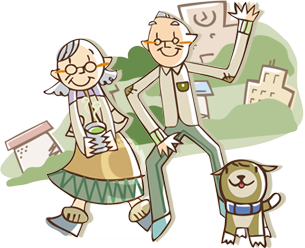明治32年(1899)~平成9年(1997)
田辺市生まれ
実践栄養学の先駆者、女子栄養大学の創立者
明治32年(1899)、本宮村(現:田辺市)に生まれる。大正3年(1914)14歳のとき、母が急性肺炎で亡くなったことに大きな衝撃をうけ医師になることを決意、大正10年(1921)東京女子医学専門学校を受験し、1番の成績で入学する。
大正15年(1926)、同郷の東京帝国大学医学部教授の島薗順次郎内科学教室に入局し、当時の日本に蔓延していた脚気治療を研究する。その中で、胚芽米にビタミンB1が多く含まれることを証明し、胚芽米の普及につとめ脚気予防に大きく貢献した。
食事で健康が取り戻せるという発見に感激した綾は、その後栄養学に人生を捧げることとなった。
昭和5年(1930)、島薗研究室の先輩であった香川昇三と結婚、昭和8年(1933)に「すべての人が健康で、そして幸せであるように」との思いで昇三とともに家庭食養研究会を設立し、昭和12年(1937)には名称を「女子栄養学園」に改める。昭和20年(1945)学園は空襲により焼失、しかし、戦後の昭和22年(1947)周囲の人々の助けもあり学園を再建、翌年に財団法人香川栄養学園を設立した。このころ、綾は「5つの食品群」を提唱、また、200ccの計量カップ、15cc、5ccの計量スプーンを考案している。
昭和25年(1950)、新しく短期大学の制度が施行され女子栄養短期大学を創立、昭和31年(1956)に夜間部、昭和36年(1961)に4年制の女子栄養大学、昭和44年(1969)に大学院を創立した。
料理カード、計量カップ、計量スプーン、四群点数法などを考案し、生活に根ざした実践栄養学という新しい分野を切り開いた香川綾は、平成9年(1997)98歳で亡くなった。