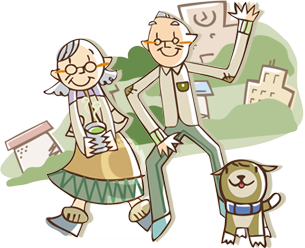有田川町(杉野原)
【魚(鯖)飯】
「荒神さんの餅まき」の当日は、昼食に集団作業で「魚(鯖)飯」を作る。現在は20人前ほど作っている。
御飯に塩鯖を入れて炊きあげて、ねぎをかけて食べる。1升に1本くらいの割合。
その後、炊き上がって身をほぐして混ぜたら出来上がり。これは、郷土料理であり、様々な行事(会式)で食される。「荒神さん」のときは、では 2升分くらい炊いたりしている。
準備・後始末に手間がかからなく、みんなで食するために。また、山間部であったため、会式の時には魚飯(鯖など)は、ハレの日の食べ物だったと思われる。
【柿の葉寿司】
柿の葉を使った柿の葉寿司も作る。種類は鯖・わさび・じゃこ(川魚のこと)など
【けんちん】
正月や御田の舞の時に作る。
【ジャジマメ】
大豆を炒って。砂糖醤油にジュッという感じで入れる。昔は正月にも食べたが、今は告別式の時など「いっこん酒」とともに回ってくる。
【じゃこずし】
川魚の押しずし
「じゃこ」とは鮎以外の川魚で、例えば川むつなど 夏にほとんどとれる。
<押し寿司の作り方>
すし飯にかやくをおき、柿の葉で包んで、それを樽に外側からぐるっと中心へ円を描くように並べていき、一段目が箱にいっぱいになったら2段目というように、段を重ねて、上から重しをしてつくる。芭蕉の葉でも作った。うえのかやくがじゃこになったら、ジャコ飯。ジャコ飯のじゃこは甘辛く炊く。じゃこがちょっと高級になったら、鮎に変わる。鮎をおしたら鮎寿司。また、番茶でジャコを炊いたりするときもあった。
川魚をちょっと干しておいて、いったんあぶって、甘辛く炊く。
いまは、ジャコを取る人はあまりいない。寒じゃこが美味しい。
鮎以外の魚をジャコという。おいかわ、川むつがほとんどである。
ごり(はぜ)を佃煮にして、山椒でちょっと味付て食べたりもした。